第1編 この法律全体で言えること
第一編 総則
第5章 取引や約束事について
第五章 法律行為
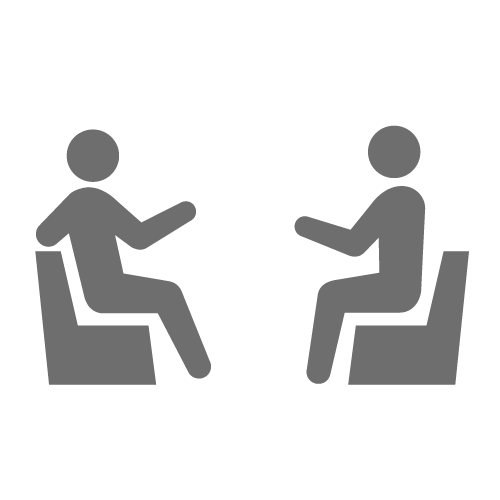
第1編 第6章 期間を計算する時の注意事項
第1編 第4章 物について
第1節 全般に言えること
第一節 総則
みんなのために
- 第90条重要
- 人々の暮らしを乱し、世の中のためにならない取引や約束事は、成立させずに無効とします。
“人々の暮らしを守り、世の中のために良いこと”を《公序良俗》といいます。
原文
法律のオススメとは違う契約
- 第91条
- 契約を結ぼうとする当事者が納得しているならば、世のためにならないものでなければ、自分たちで決めた内容が法律上のオススメとは異なっても問題ありません。
“法律的にオススメの契約内容”を《任意規定》といいます。
“どのような内容の契約にするかを相手に伝えること”を《意思表示》といいます。
原文
法律のオススメとは違うしきたり
- 第92条
- 法律上のオススメと違っていても、契約を結ぼうとしている当事者同士が納得し、世のためにならないものでなければ、世間で広く親しまれているしきたりに従ってもかまいません。
原文
第2節 互いに希望を確かめ合う取引
第二節 意思表示
嘘や冗談が伝わらないと本気になります
- 第93条重要難文
-
だますつもりはないまでも、相手が喜ぶようなことを相手にいうことがありますね。
たとえ嘘や冗談のつもりで自分の本心とは違う内容を相手に伝えて取引や約束事をした場合、その契約は有効です。そのことだけで取り消しにはなりません。
もちろんそうは言っても、言われた相手が嘘や冗談を言ってるなと分かる場合やよくよく考えたら本気で言ってるわけがない場合は、取り消して、無かったことにできます。 - 2
- 無関係の人に影響が及ぶ場合は、取引や約束事を取り消して、なかったことにはできなくなります。
嘘や冗談を言って自分の本心とは違う内容で契約をしたり“自分の本心を出さずに契約条件”とすることを《心裡留保》といいます。
原文
偽装の取引や約束事
- 第94条重要
- 当人たちが合意の上で取引や約束事を装っている場合、もちろん装っているだけなので取引も約束事も成立していません。
- 2重要
- 成立しているように偽装した取引や約束事により無関係の人に影響が及ぶ場合は、取引や約束事を取り消して、なかったことにはできなくなります。
“偽装の取引や約束事”のことを《虚偽表示》といいます。広告の虚偽表示とはやや意味が異なりますね。
原文
思い違い
- 第95条重要
- 次のような思い違いによって取引や約束事をしてしまった場合、どうするつもりだったのかを聞いたり、一般社会の常識で判断してやむを得ない場合は取り消すことが認められます。
- 一
- 見間違い、聞き間違い、言い間違い、書き間違い
- 二
- 思い込み、勘違い
- 2
- 誰の目にも明らかに、思い違いだとわかる場合でなければ、取り消しはできません。
- 3
- 重大な落ち度のせいで、思い違いをした場合は、次のようなケースでなければ、取り消しはできません。
- 一
- 取引や約束事の相手が思い違いに気づいていたケースや、取引の相手にも重大な落ち度があって思い違いに気づかなかったケース
- 二
- 取引や約束事の相手も同じ思い込みをしていたケース
- 4
- 取引や約束事に無関係の人は、思い違いのことを知らず、その人に落ち度もない場合、取り消しによって悪影響が出る場合は、取り消しは認められなくなります。
思い違いや勘違いのことを《錯誤》といいます。
原文
詐欺や強迫されたら
- 第96条重要
- 詐欺で騙されたり、強迫で脅されてした契約は、後からでもその契約をキャンセルにしてはじめから契約は無かったことにすることができます。
- 2重要
-
たとえ詐欺に関わる契約であったとしても、それを知らないもの同士が当事者となる契約はキャンセルにすることはできません。
しかし当事者の一方が詐欺に関わる契約であることを知っていたり、知ることができる立場にあれば、もう一方の人は契約をキャンセルにしてはじめから契約は無かったことにすることができます。 - 3
- 詐欺だと気付き、キャンセルを訴えても、詐欺のことを知らず、詐欺のことに関して落ち度も無い無関係の人に悪影響が及ぶ場合は、キャンセルができません。
原文
その場にいない人との取引や約束事
- 第97条
- 取引や約束事をする場合、相手がその知らせが届いた時から「契約は有効」ということにします。
- 2
- 正当な理由がないのに、手紙や電話、Eメールの受け取りを拒否した場合、その知らせが普通に届く時点で届いていたものと判断されます。
- 3
- 知らせを発信した時点で問題がなければ、相手が取引や約束事に関する知らせを受け取る前に、送った人が亡くなったり、「契約できない人になった」と裁判所に認められたとしても、取引や約束事がキャンセルになることはありません。
原文
相手がわからない時には《公示》を
- 第98条
- 自分が誰と取引や約束事をしたのかわからない(わからなくなった)場合、あるいはその相手がどこにいるのかわからない場合、その取引や約束事をすすめるためには《公示》という方法があります。
- 2
-
《公示》は、「裁判所の掲示板に掲示する」「掲示が行われたことを官報に掲載する」という2つの方法で行います。
ただし裁判所が適切な対応と判断した時は、「官報掲載」の代わりに、「市役所・区役所・町村役場、あるいはそういった公の施設の掲示板に掲載しなさい」というを命令を出すことができます。 - 3
-
《公示》をしてから2週間が経った時点で《公示》は相手に伝わったとみなされます。
詳しくは、「(何回か掲載された場合はその最後の)官報に掲載された日」から、または「官報への掲載の代わりに行った掲示板での掲示を始めた日」から2週間が経った時点です。
しかし、もし相手がわからないとか連絡先がわからない理由が自分の勘違いの場合や、相手先の事をろくに調べもせずに《公示》をしたとしてもそれが相手に伝わったとは認められませんので、有効になりません。 - 4
-
《公示》の手続きを行う場合に届け出るのは簡易裁判所で、どこの簡易裁判所に届け出るかは、
- 相手の名前や住所がわからない時:自分の住所を管轄する簡易裁判所
- 相手の現住所や居場所がわからない時:相手が最後にいたと確認できた住所を管轄する簡易裁判所
- 5
- 《公示》は有料で、予めその費用を裁判所に支払うことが必要です。
原文
相手が未成年や成年被後見人の場合
- 第98条の2
-
相手が、未成年や、契約できる状態でなかったり、成年被後見人の場合は、自分が取引や約束事のことを相手にきちんと伝えたつもりでも、相手に「知らない」とか「覚えがない」と言われてしまうと、その取引や約束事は無かったことになってしまいます。
とはいえ、次の人に「わかりました」といってもらえば、その取引や約束事はちゃんと成立したことになります。 - 一
- 相手の親などの法定代理人
- 二
- 相手が、ちゃんと契約できる状態や、成年被後見人ではなくなった場合の本人
原文
第3節 自分のかわりに別の人が
第三節 代理
代理を任したら
- 第99条重要
-
ある取引や約束事について自分の代わりを代理人に任したら、自分の権限も引き渡すことになります。
その結果、代理人が行なった取引や約束事は、自分がしたのと同じ扱いとなり、その利益も義務も責任も全て自分が受けることとなります。 - 2重要
- 逆に相手が代理人に対して取引や約束事を持ちかけた場合でも、代理人がそれを受け入れれば、その結果は自分に及ぶこととなります。
代わりの人が自分に成り代わって取引や約束事をすることを《代理》、その人のことを《代理人》と呼びます。
原文
代理と名乗らずにした取引や約束事は
- 第100条
-
代理人のくせに「代理ですよ」ということを相手に名乗らないと、相手は代理だとはわかりません。
相手は当事者だと思って取引や約束事をしたつもりですから、その契約は代理人自身がしたこととみなされ、代理を任せた人とは無関係ということになります。
しかし、あえて「代理ですよ」と言うまでもなく相手が「代理でしょ」とわかりそうな場合、もしくは互いにわかっている場合は、もちろん代理となります。
原文
代理人が“うっかり”わかっていなければ
- 第101条
-
代理人が以下の事情をきちんと把握することは、本人がその取引や約束事をするかしないかに重大に関わります。
- 約束や取引をする本人の意思
- 詐欺や脅迫
- 取引に関わる重要な事項
- 2
- 相手が取引や約束事をする意思がなかったり、詐欺や脅迫を受けていた場合、代理人がうっかりしていてその事情をわかっていないならば、その取引や約束事には重大な欠陥があるということになります。
- 3
-
依頼した本人が重大な欠陥の事情をわかっていたならば、「代理人がうっかりその事情をわかっていないから〜」ということを理由にして取引や約束事にクレームをつけることはできません。
本人がうっかりして重大な欠陥の事情を気づけなかった場合についても「代理人がうっかりその事情をわかっていないから〜」ということを理由にして取引や約束事にクレームをつけることはできません。
重大な欠陥のことを《瑕疵》といいます。
原文
代理はだれにでも任せられます
- 第102条
-
代理人を任せるにあたっては、その人が“子供”であっても、成年被後見人や被保佐人・被補助人であっても問題ありません。
このような代理人が取引や約束事をした場合、それを理由に取り消すことは認められません。
もちろん、代理人を任せた当人が、成年被後見人や被保佐人・被補助人であれば、それを理由にして取り消すことが認められます。
成人で、被××人ではない人のことを《行為能力者》といいます。
原文
権限が決められていなくても代理人ができること
- 第103条
- 特に代理人に何か条件をつけていない場合でも、代理人は次のようなことをする権限があります。
- 2
- ありのままにする行為《保存行為》
- 3
- 代理人がしたことで、物や権利がオリジナルとはかけ離れてしまわない程度に、それを利用したり、よりよく改良しようとする行為《利用・改善行為》
《保存行為》の例:修理やお手入れ
《利用・改善行為》の例:現金の預金化、賃貸物件のリフォーム
《利用・改善行為》の例:現金の預金化、賃貸物件のリフォーム
原文
代理人が、そのまた代理を頼むには
- 第104条
-
代理を任された人に何かやむを得ない事情がある場合に限って、代理人のそのまた代理をしてくれる人を頼むことができます。
やむを得ないほどの理由がない場合は、代理人を頼んだ人がOKを出した時のみ、代理人のそのまた代理をしてくれる人を頼むことができます。
人から頼まれて代理をする人のことを《委任代理人》といいます。
代理人に代わって依頼者の代理をしてくれる人を《復代理人》といいます。
原文
法定代理人が、そのまた代理を頼むには
- 第105条
-
未成年の親や、《成年後見人》は、法的に認められた《法定代理人》という立場になります。
彼らは特に事情がなくても、誰からの指図も受けずに自分の責任でそのまた代理を頼むことができます。
やむを得ない事情があってそのまた代理人を頼んだ時は、その人に任せた責任者としてちゃんと代理を務めているか監督しなければいけません。
未成年の保護者や成年後見人のことを《法定代理人》といいます。
原文
代理人の、そのまた代理の人は
- 第106条
- 代理人のそのまた代理を務める人は、直接元の依頼者の代理を務めることになります。
- 2
- 代理人のそのまた代理を務める人は、依頼者や依頼者と取引をしようとする人に対して、その権限の範囲内においては代理人と同様の権利が有り、代理人と同様の義務を果たさなければなりません。
原文
それ代理じゃないよね、と見られると
- 第107条
- 相手が明らかに「代理というよりも自分や他の人のために活動してるよね」とわかってしまう取引や約束事は、代理を任せた当人は取引をしたことになりません。
原文
本人のためにならない代理人
- 第108条
-
取引や約束事をしようとする本人が、その契約相手の代理人になることは認められず、自分と自分が契約したものとみなされます。
取引や約束事の代理を任された代理人が、その契約相手の代理人になることは認められず、任せた本人と代理人が契約したものとみなされます。
ただし、次の場合は本人や代理人が契約相手の代理人になることが認められます。- 依頼者との交渉をするまでもなく債務を果たすだけの取引の場合
- 予め、取引の相手が代理人となることを認めていた場合
- 2
-
取引や約束事の相手が自分の代理人になる場合に限らず、自分の代理人が自分のためにならないことをわざわざした場合は、相手とその代理人自身との間で契約をしたものとみなされます。
ただし、予め自分のためにならない取引や約束事であることを認めていた場合は、相手と自分の間で契約したものと認められます。
代理人が契約相手となることを《自己契約》といいます。
契約する当事者双方の代理人となることを《双方代理》といいます。
原文
代理だと言っておきながら
- 第109条難文
-
本当はまだ代理を任せていないのに、自分は「ある件について、その人に代理を任せた」と伝えていたら、その人が他の人とその件について取引や約束事をしたことは、自分が責任を負うことなります。
しかし、契約を結んだ相手が、本当は代理を任されていないと知っていた場合や、本当は代理人ではないことをうっかり見逃した場合には、自分が責任を負う必要はありません。 - 2
-
「ある件について、その人に代理を任せた」と伝えていて、ある件の範囲内についての取引や約束事に関しては任せた自分が責任を負う場合に、この件の範囲を超えた事まで取引や約束事をしてきてしまったら、その責任の境界は次の通りとします。
- 相手が、「その事も任された代理人だ」と信じる正当な理由がある場合、代理を任せていなくても自分が責任を負うことになります。
- 相手が、「その事も任された代理人だ」と信じる正当な理由がない場合、自分は責任を追わず、代理人として契約をした人が責任を負うことになります。
本当は代理を任されていないのに代理人のようにふるまうことを《表見代理》といいます。
原文
権限の無い人と契約をしたら
- 第110条
- 本当は依頼人から権限を与えられていないのに、ちゃんと依頼を受けた代理人だと信じて取引や約束事をした場合は、「代理権を与えられているもの」として契約をしたこととなり、この件では代理人の依頼者が責任を負うこととなります。
相手が「この代理人は代理の依頼は受けていないな」と知っていて契約をした場合は、依頼人が責任を負う必要はありません。
原文
代理人ではなくなるために
- 第111条
- 次の場合に代理の依頼は終了し、代理人ではなくなります。
- 一
- 依頼人が亡くなった時
- 二
- 代理人が亡くなった時や、代理人が破産した時、被後見人とジャッジされた時
- 2
- 依頼されてなった代理人の場合で、その依頼が終了した時
原文
代理人ではなくなった後に代理人として振る舞うと
- 第112条
-
任されていた代理の任務が終わって、代理の権利がないはずなのに、まだ任されている代理人を装って取引や約束事を行ったら、相手が代理の任務が終わっていたことを知らない場合は、代理を任せた本人と契約をしたことになります。
知らないとはいえ、代理の任務が終わっていたことをうっかりしていて気づかなかった場合は、必ずしも代理を任せた本人と契約をしたことにはなりません。 - 2
-
任務が終わっていないことに加え、本来任されていないことまで任されている代理人だと装って取引や約束事を行ったら、相手がそのことまで任されている代理人であると信じてもやむをえない事情があれば、代理を任せた本人と契約をしたことになります。
信用するまでに至らない場合は、その代理人の当人と契約をしたことになります。
原文
代理人のふりをしたら
- 第113条
- 頼まれてもいないのに代理人のふりをして取引や約束事をした場合、あらためてその当人が契約することを認めない限り、当人にその契約の恩恵や責任が及ぶことはありません。
- 2
- 契約の相手が代理人のふりだったことを知らないとしたら、必ずその相手に「代理人のふりをした人がした契約を認めるつもりがあるのかないのか」を伝えなければ、代理の依頼をされた人を通じて当人と契約をしたものとして扱われます。
代理を頼まれていない人が代理人のふりをして契約することを《無権代理》といいます。
原文
代理人のふりをされたら
- 第114条
-
“代理人のふりをした人”と契約をしたら、本当は依頼をしていなくても契約したことになる本人に対して、「時間を与えるからその期限までに正式に依頼をするかしないか、返事をしてくれ!」と回答を求めることができます。
もしその締め切りまでに返事がなければ、「依頼する気は無い」とみなされます。
原文
代理人としらずに契約を結んだら
- 第115条
-
代理人のふりをした人と取引や約束事をした人は、本当は依頼をしていなくても契約したことになる本人が「あらためて依頼をするか、しないか」の返事をする前ならば、契約の取り消しができます。
ただし、代理人のふりだと知ってて契約を結んだのなら、そのような取り消しはできません。
原文
あらためて代理を依頼して契約を認めたら
- 第116条
-
契約を結んだ後、代理を依頼をしたことにして「その契約はOKだ」と認めた場合、結ばれた時点にさかのぼってその契約はスタートしていたこととなります。
しかし認めるか認めないかはっきりしない間に、もしこの件の部外者が関わった場合、そこで発生した権利は守らなければなりません。
原文
代理人のふりをした人にのしかかる責任
- 第117条
-
代理を任されていないにもかかわらず、代理人として取引や約束事の契約を結んだ以上、相手が「契約通りにしてほしい」と言われれば何とかする責任を追うことになります。
相手が「何ともならないなら損害倍書をしてほしい」と言われれば、お金で解決する責任を負うことになります。
もちろん、代理を任されたことを証明できれば、そのような責任を負う必要はありません。 - 2
- 次のケースに該当する場合は、契約をした代理人であっても、上記のような責任を負う必要はありません。
- 一
- 契約相手が代理人としての権利を持っていないことを知っていた場合
- 二
- そもそも自分には代理の権利があると思っていて、契約相手が代理人としての権利を持っていないことをうっかり気づかなかった場合
- 三
- 代理の権利を持っていない代理人が、未成年や成年被後見人などの取引や約束事の制限を受ける立場だった場合
原文
一方的な約束で代理人のふりをされたら
- 第118条難文
-
依頼されていない人が代理をして《単独行為》をした場合は、約束事は無効になります。
しかし、「代理人のふりをして約束事をしてきた」ような状況や、「代理人ではない人に代理人として約束事をもちかけられた」状況で《単独行為》の約束事をしても、当人が約束事に同意をした場合や、代理していないことがだれからも問題にならない場合に限り、その対応として第113条から第117条までの規定を同じように適用することが認められます。
これにより、当人が約束事の責任を負わずに正式に無効としたり、約束をしたあとでも当人が約束事を認めて有効とすることもできます。
相手の意向を考慮する必要がなく、自分だけの意思で取り決めできる約束事や取引のことを《単独行為》といいます。
《単独行為》の例としては、《遺言》や、《契約途中の解除》などがあるようです。
原文
第4節 はじめから無かったことにする場合と途中で辞める場合
第四節 無効及び取消し
無効は無効
- 第119条
-
“取引や約束事”を結び直したとしても、内容的に無効な“取引や約束事”だったら、無効が有効になることはありません。
「このままでは“取引や約束事”は無効なままだから、ちゃんとした内容に手直しした“取引や約束事”をすれば、ようやく新たに有効な“取引や約束事”として認められることとなります。
原文
取り消しができる人
- 第120条
-
未成年者や成年被後見人らが要望したら、彼らを相手にした取引や約束事は取り消しになります。
保佐人以外で、彼らの法定代理人が要望した場合も、そのような取引や約束事は取り消しになります。
保佐人に同意が必要なケースであれば、保佐人が要望した場合も、そのような取引や約束事は取り消しになります。
彼らの権利を引き継いだ人が要望した場合も、未成年者や成年被後見人らを相手にした取引や約束事は取り消しになります。 - 2
-
思い違いや勘違い、詐欺や脅迫により問題となる取引や約束事をした本人が要望した場合、その取引や約束事は取り消しになります。
問題のある取引や約束事をした本人の代理人や、その権利を引き継いだ人が要望した場合も、その取引や約束事は取り消しになります。
相続や事業継承などによりその権利を引き継いだ人のことを《承継人》といいます。
原文
取り消しをすると、はじめからしなかったことに
- 第121条
- 取り消しを行った場合は、契約の時点にさかのぼって、そもそも取引や約束事はしなかった、ということになります。
原文
取り消したんだから、元に戻して
- 第121条の2
- 取引や約束事を取り消したり、無効にした際、相手からすでに何かをしてもらっていたら、相手に返したり、元に戻す必要があります。
- 2
-
相手から、一方的に何かをしてもらえると本気で信用して受け取ったのに、実は無効だったという場合は、すでにもらって手元に残っている分については相手に返す必要があります。
しかし、本当はもらえるはずはないとか、取り消されるだろうなと思っていた場合は、もらった分全てを相手に返したり、完全に元に戻す必要があります。 - 3
-
自分の意思を失っている人から何かをしてもらったら、してもらって手元に残っている分については返す必要があります。
取引や約束事に制限を受ける立場の相手から何かをしてもらった場合も、してもらって手元に残っている分については返す必要があります。
“相手に返したり、元に戻す”ことを《原状回復》といいます。
原文
ひとたび、取り消しはしなくてOKといったら
- 第122条
- いかに取り消しが認められるとしても、彼らの法定代理人や彼らの権利を引き継いだ人によってひとたび「取り消しをしないで、このままでOK」とした場合は、以降は二度と取り消しできなくなります。
「取り消しをしないで、このままOK」と認めることを《追認》といいます。
原文
取り消しや追認の方法
- 第123条
- 取引や約束事の相手がわかっている時は、その相手に向かってこの取引や約束事は「取り消します」とか「このままでOKです」と伝えてください。
原文
本人が追認をするには
- 第124条
-
取り消し可能な要因が残っている間は、《追認》をしても効力が生じません。
取り消し可能な要因が無くなったとしても、本人が《追認》できるということを認識するまでは、《追認》の効力が生じません。 - 2
- 次のケースでは、取り消し可能な要因が残っていたとしても、追認の効力が生じます。
- 一
- 法定代理人か、その本人の保佐人や補助人が追認をするケース。
- 二
-
法定代理人か、保佐人や補助人の同意を得た上で、本人が追認をするケース。
ただし、本人が成年被後見人の場合は、追認できる状態ではないので、このケースでも追認の効力は生じません。
“取り消し”可能な要因とは、追認した本人がまだ未成年のままで判断が不十分だったり、詐欺にあっていることが判明していない状態であることのようです。
原文
事実上の追認事項
- 第125条
-
《追認》できる状態にある時、“取引や約束事”に関して次の行為をした場合には、事実上の《追認》をしたものとみなします。
ただし、異議をとなえると《追認》をしたとはみなされません。 - 一
- 約束事の一部でも履行があった
- 二
- 相手に約束事を「履行してほしい」と請求した
- 三
- 相手との契約を更改した
- 四
- 担保を供与した
- 五
- 得られた権利を一部でも自ら人に譲渡した
- 六
- 強制執行が行われた
原文
取消権の時効について
- 第126条
-
《追認》できる時点から五年間行使されない場合、時効により取消の権利が消滅します。
同様に“取引や約束事”をした時点から20年を経過した時も、時効により取消の権利が消滅します。
原文
第5節 条件と期限
第五節 条件及び期限
条件の成就の仕方と効力の関係について
- 第127条
- 《停止条件付法律行為》とは、「条件がかなったら、“なにか”をする」という約束がついた取引のことです。
- 2
- 《解除条件付法律行為》とは、「条件がかなったら、“なにか”をしない」または「条件がかなわなかったら、“なにか”をする」という約束がついた取引のことです。
- 3
- 当事者の間で話し合いがついている場合は、「条件がかなった時よりも以前にさかのぼって効力が発揮することにしよう」という契約も有効です。
原文
条件がかなう前に相手方の利益をそこなってはならない
- 第128条
- 条件がかなうかどうかが未定の時点において、条件の結果により相手に利益を提供する人は、その利益を損なうようなことをしてはいけません。
原文
条件がかなうかどうか未定でも
- 第129条
- 他の規定にもよりますが、条件の結果により義務を負ったりや権利を得られる人は条件がかなうかどうかが未定の時点であっても、その権利や義務を「人に譲ったり」、「相続させたり」、「時効にならないように管理したり」、あるいはその権利を「担保として差し出す」ことも可能です。
原文
条件成就を邪魔されたら
- 第130条
- 条件がかなうことにより不利になる側の人にわざと条件成就を邪魔されたら、相手としては「条件はかなった」とみなしてかまいません。
- 2
- 条件がかなうことにより有利になる側の人が不正に条件を成就させたら、相手としては「条件はかなわなかった」とみなしてかまいません。
原文
条件の結果が出ていても
- 第131条
- 条件をつけた時にはすでに満たされていたら、《停止条件》付きの契約なら即座に「Go!」となり、《解除条件》付きの契約ならそのまま「Stop!」となります。
- 2
- 条件をつけた時にはすでに満たされることはありえなかったら、《停止条件》付きの契約ならそのまま「Stop!」となり、《解除条件》付きの契約なら即座に「Go!」となります。
- 3
-
条件の結果がすでに出ていたとしても、当事者の間でその結果が判明するまでの間は、結果が出ていないことと同じ状態と考えられます。
したがってその間は、相手方の利益を損なうようなことをしてはいけないし、得られる義務や権利を譲ったりすることも可能です。
原文
不法な条件
- 第132条
- 法律違反の条件をつけたり、わざわざ法律違反をしないことを条件につけた取引や約束事は無効です。
原文
誰にもできない条件
- 第133条
- 「誰にもできないことができたら、こっちもしてあげよう」という条件をつけた取引や約束事は無効です。
- 2
- 「誰にもできないことができたら、こっちはやめてあげよう」とか「誰にもできないことをしなければ、こっちがしてもらうぞ」という取引や約束事には、条件が付いていないことになります。
原文
気分が条件は無効
- 第134条
- 条件を出した人の気分や主観で基準が決まるようなあいまいな条件は、無効です。
原文
期限が来るまで
- 第135条
-
契約の内容に“開始の時期”を設定したら、その時期が来るまで契約の内容はスタートしません。
開始時期より「早く始めろ!」と催促することも認められません。 - 2
- 契約の内容に“終了の時期”を設定したら、その時期が来た時、契約の内容は終了します。
原文
期限が来る前に
- 第136条
- 契約で義務を負う人は、契約の期限が来るまで猶予が与えられたものと判断できます。
- 2
- 互いに「迷惑をかけない」ならば、あえてその期限にとらわれずに、さっさと義務を果たしてもかまいません。
原文
期限が来ていなくても
- 第137条
- 契約で“義務を負う人”が次の状態になると、期限が来ているかどうかを問わず、義務を果たさなければならくなります。
- 一
- “義務を負う人”が破産した時
- 二
- “義務を負う人”の担保がなくなったり、少なくなったり、担保の価値が減った時
- 三
- “義務を負う人”が担保を差し出さなければならないのに、差し出さない時
この場合の“義務を負う人”とは、主にお金を支払わなければならない人のことですね。
原文
第1編 第6章 期間を計算する時の注意事項
第1編 第4章 物について












4 件のコメント:
民法第96条第一項の、
意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、
又はその所在を知ることができないときは、
公示の方法によってすることができる。
について、「相手方を知ることができず」とは
どういう意味でしょうか?
当方法律学者でも弁護士でもありませんので、あしからず。
コンビニで商品を買うとき、現金を渡せばわざわざ自分が誰なのかを名乗る必要がありません。
コンビニ側からすれば、「相手方を知ることができず」となります。
もし、コンビニ側が代金を余分に受け取ってしまったり、渡した商品に問題があって交換が必要な場合にはお客を特定しなければなりません。
そんなケースでの解決の方法の一つとして「公示」がありますよ、ということでいかがでしょうか。
民法第131条3項の、
前二項に規定する場合において、
当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、
第128条及び第129条の規定を準用する。
について、
既に条件が成就しているor成就しないことが確定しているのに、
当事者達が知らない状況などあるのでしょうか?
例えば、
夫が妻に「この宝くじが当っていたら、世界一周旅行に連れて行くよ」と約束していたものの、二人とも当選発表の日が来ていたことを忘れていた場合。
兄が弟に「父が死んでも自分は遺産を放棄する。」と言っていたものの、父は災害に巻き込まれて生死も行方も不明になってしまった場合。
ある国の政府から「コロナワクチンが完成したら、全ての国民に摂取させます」との発表に対して、某国が陰謀によりワクチン完成の事実が隠匿された場合。
なんていかがでしょうか。
コメントを投稿